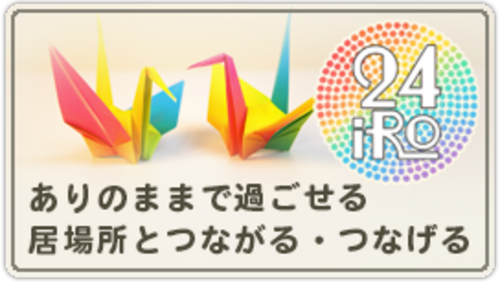話を聞いてもらえないとき
人に何かを伝えようとしても、相手が耳を傾けてくれないときがあります。
言葉を選び、タイミングを整えても、反応が薄い。
相槌はあっても心ここにあらずで、こちらの意図が届いていない感覚だけが残る。
教育や支援の現場でも、この「聞いてもらえない感覚」に直面することは少なくありません。
それは相手が意地悪をしているわけでも、必ずしも無関心なわけでもない。
多くの場合、その背景には言葉のやり取りを支える構造が整っていないという事実があります。
話を聞いてもらえないとき、人は往々にして言葉を増やそうとします。
説明を補い、例えを重ね、説得のための情報を盛り込む。
しかし、それで状況が好転することは稀です。なぜなら、届かない原因は言葉の中身ではなく、関係の位置と距離にあることが多いからです。
ここで必要なのは、相手の態度や性格を変えようとすることではなく、言葉が届くための構造を整える視点です。話を聞いてもらえない時間を、諦めや苛立ちで終わらせず、届く関係へと変えていくための方法を考えていきます。
言葉を選び、タイミングを整えても、反応が薄い。
相槌はあっても心ここにあらずで、こちらの意図が届いていない感覚だけが残る。
教育や支援の現場でも、この「聞いてもらえない感覚」に直面することは少なくありません。
それは相手が意地悪をしているわけでも、必ずしも無関心なわけでもない。
多くの場合、その背景には言葉のやり取りを支える構造が整っていないという事実があります。
話を聞いてもらえないとき、人は往々にして言葉を増やそうとします。
説明を補い、例えを重ね、説得のための情報を盛り込む。
しかし、それで状況が好転することは稀です。なぜなら、届かない原因は言葉の中身ではなく、関係の位置と距離にあることが多いからです。
ここで必要なのは、相手の態度や性格を変えようとすることではなく、言葉が届くための構造を整える視点です。話を聞いてもらえない時間を、諦めや苛立ちで終わらせず、届く関係へと変えていくための方法を考えていきます。