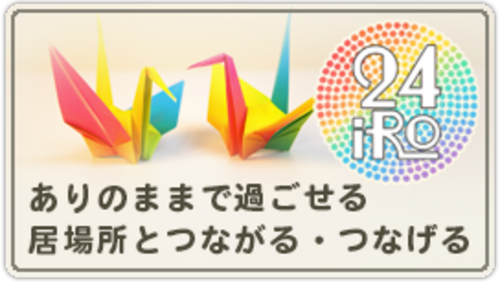何を考えているかわからない
日常の関わりの中で、「この人は何を考えているのだろう」と感じる瞬間は少なくありません。
相手が沈黙している、表情が変わらない、言葉を選びすぎて本心が見えない──そんな状態が続くと、関わる側は戸惑いや不安を抱きます。
「自分に不満があるのではないか」
「何か隠しているのではないか」
「本音を言うつもりがないのではないか」
こうした推測は、時間とともに膨らんでいきます。特に教育や支援の場では、相手の内面が見えないことが指導やサポートの質に直結するため、「わからないままにしておく」ことへの不安は大きくなります。
結果として、相手を理解しようとする姿勢が、知らず知らずのうちに境界を踏み越える行動へとつながることがあります。
しかし、この「何を考えているかわからない」という感覚は、必ずしも相手の意図や性格だけで生じるわけではありません。
多くの場合、その背景には関係の構造や境界の状態が深く関わっています。
構造が整っていないまま相手の考えを探ろうとすれば、無理な引き出しや過剰な詮索となり、かえって相手の口を閉ざすことにもなりかねません。
見えないものを見えるようにするためには、感情的な反応ではなく、まず構造的な見立てから状況を理解する必要があります。
「わからないこと」は必ずしも欠点や危険信号ではなく、関係を整えるきっかけになるのです。
相手が沈黙している、表情が変わらない、言葉を選びすぎて本心が見えない──そんな状態が続くと、関わる側は戸惑いや不安を抱きます。
「自分に不満があるのではないか」
「何か隠しているのではないか」
「本音を言うつもりがないのではないか」
こうした推測は、時間とともに膨らんでいきます。特に教育や支援の場では、相手の内面が見えないことが指導やサポートの質に直結するため、「わからないままにしておく」ことへの不安は大きくなります。
結果として、相手を理解しようとする姿勢が、知らず知らずのうちに境界を踏み越える行動へとつながることがあります。
しかし、この「何を考えているかわからない」という感覚は、必ずしも相手の意図や性格だけで生じるわけではありません。
多くの場合、その背景には関係の構造や境界の状態が深く関わっています。
構造が整っていないまま相手の考えを探ろうとすれば、無理な引き出しや過剰な詮索となり、かえって相手の口を閉ざすことにもなりかねません。
見えないものを見えるようにするためには、感情的な反応ではなく、まず構造的な見立てから状況を理解する必要があります。
「わからないこと」は必ずしも欠点や危険信号ではなく、関係を整えるきっかけになるのです。